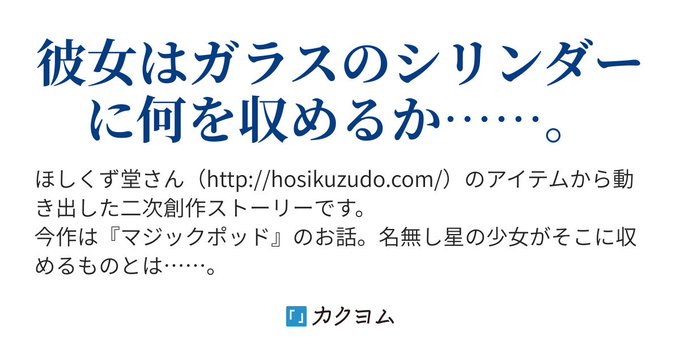
—-
『名無し星と命の記憶』 著:かざき
—-
この辺境の小さな星はそこに住む僅かな人々の日常が穏やかに続く場所だが、時々どこからか訪れる旅人の姿を見かけることがあった。
その日、村に広場に姿を現したのは不思議な装飾が施された外套をまとった初老の男だった。
傍らにはいくつかの箱が積まれた荷台がひとつ。
男は広場に適当な場所を見つけると積み荷を手早く広げ始める。物珍しさに人が集まり始め男の周りに人だかりが出来る頃には、小さな屋台のようなものが組み上がっていた。
「さあさ、寄ってらっしゃい。数々の世界を巡り集めた珍しい品、珍しい生き物をご覧に入れましょう」
男は周りの人々にそう呼びかけると、一呼吸おいてから演技がかった口調で持ち込んだ品を紹介し始めた。
「あるじー、久しぶりに誰か来てるみたいだね」
「何だろ? あんなに人が集まるの、珍しいね」
材料の採集を終えて村に戻ってきたレルタとクランは遠目にも分かる広場の人だかりを見つけてそんな言葉を交わした。広場に旅人がやってきて村人が集まること自体は珍しいことではなかったが、老若男女というのは滅多にないことだった。
「お次はこちら。美しい羽と極上の歌声を持つ星鳴き鳥」
2人が広場に近づくとそんな声が聞こえた。
人だかりの隙間から金色の籠に入れられた瑠璃色の美しい鳥の姿がレルタの目に入る。その艶やかな羽の中には夜空の星のような金銀の小さな輝きが散りばめられていた。その姿で人々の視線を惹きつけた鳥は、その場の騒めきを物ともせず歌うような澄んだ鳴き声を響かせた。
「寄ってく?」
クランの問いにレルタは渋い顔をして首を横に振る。好奇心旺盛な彼女にしては珍しい反応だ。
「んー、なんかね嫌な感じ。悲しい……かな? それとも、苦しい? 胸の奥がギュってなる」
レルタは聞こえてきた鳥の声に感じたことを表す言葉を探した。
人々の歓声。
いつになく賑わう広場。
そんな明るい雰囲気の中、レルタは表情を曇らせたままその場を後にしたのだった。
★☆★
翌日。旅の男は昼過ぎまで村唯一の宿でのんびり過ごすと、その日は店を広げることなく旅立っていったらしい。工房を訪れる客から昨日の話の数々と一緒にそんな話を聞く。
そんな一日が終わろうとした頃、その日最後の客が工房の扉を開けた。
「レルタ、お願いがあるの」
訪れたのは数人の子供たちだった。その中の1人が小さな籠を大切そうに抱えている。
「この子ね、さっきから元気がないの」
「レルタの魔法の道具で助けてあげられる?」
籠の中には瑠璃色の鳥が1羽。だが昨日の艶やかな羽ではない、くすんだ紺色の羽を膨らませて籠の隅で目を閉じていた。
「この子、どうしたの?」
「おじさんが村を出る時にくれたんだ」
レルタの問いに子供たちが口々にその時の様子を話し始める。
子供たちは昨日の見せ物をもう一度見たくなり男のもとに集まった。しかし男は出発の時間が迫っているから店は開けられないと話し、代わりにあの鳥を子供たちにあげると言ったそうだ。
それが今日の昼頃の話。男が村を去った後、残された鳥は羽の輝きを失くし歌うこともなくなり、みるみる弱っていったというわけだ。
子供たちの話を聞きながら星鳴き鳥の様子を見ていたレルタは
「残念だけど、私じゃ『命』は治せないよ」
と静かに告げた。
「それに、この子は本当はもっと星くずに満ちた世界じゃないと生きていけない。この星の力じゃ足りないと思う」
……だから、か。
レルタは話しながらそう思った。あの時聞こえた声がただ美しいだけの歌ではなかったのだと。故郷から連れ出された悲しみか、助けを求める叫びか、あるいは最期の歌だったのか。
「鳥さん、僕たちが貰っちゃったから助からないの?」
「……それは違う。たぶんあのまま連れ回されても同じことになってた」
子供たちの中で、誰かが声にした罪悪感。うつむく子、目に涙を浮かべた子、そんな子供たち向けてレルタはいつもの穏やかな口調で諭した。
それからレルタはあの時の『嫌な感じ』の正体を認識した。己の欲の為に何かを利用し、使い捨てていく。それがどれだけ愚かなことか、取り返しのつかない何かを引き起こすことなのか、彼女は知っているような気がした。
「みんなはこの子の声、憶えてる?」
気を取り直してレルタは子供たちにそう問いかけた。子供たちはその言葉に何度も首を縦に振った。
「それならこの子に歌を聞かせてくれたお礼を言って、美しい姿も心に刻んで……そして、ちゃんとお別れしよう」
レルタはそう言うと、腰に下げていた革のケースからガラスのシリンダーを取り出しコルクの栓を抜いた。そして籠の中の消えかけた命をそっと両の掌に乗せた。
「……星は巡る」
歌うように始まる詠唱。
「はじまりは おわりへ
おわりは はじまりへ
小さな光 つなげば星座
夜空に綴る 物言わぬ 物語」
レルタの手の中で星鳴き鳥はその羽に散りばめられていた小さな星の様な光の粒となり、そしてシリンダーの中に吸い込まれていった。
「あなたの時間、守れなくてごめんね。……でも、憶えているから」
コルクの栓を閉める時、シリンダーはほんの一瞬だけ瑠璃色の光を放った。
レルタはその光の中に澄んだ美しい声を感じた。
以前、うちの子が使いますと言っていた『マジックポッド』
今回はそのお話になります。#ほしくず堂
https://t.co/9mxpsTfxKT— かざき(さっこ) (@foo_kazaki) November 10, 2019




