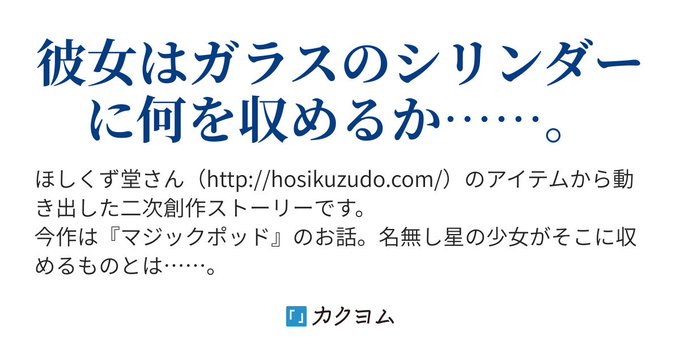【スピンオフSHOT for Mr.ray】
作:いけだ@Luche [twitter:@LucheVampire]
—————————————————————
その部屋は世界に取り残された部屋。
静かに、だけど、もの悲しい小さな部屋。
「今日はお客さんゼロかしら?」
足元でのどを鳴らす小さな猫。
その白い猫は人語をしゃべり、彼を見上げる。
「・・・いや、そうでもないさ。」
白衣を着た彼は細いタバコから紫煙をくゆらせながら、扉を見つめる。
カエルの彫刻が施された扉は真新しく、こちらから開けられた形跡は少ない。
彼は店舗のフローリングを自慢の革靴で踏みしめながら、じっと扉を見つめる。
そんな彼を見ながら、小さなため息を吐いた白猫は店内のカウンターに飛び乗る。
カウンターはここにはそぐわない、バーカウンターの様相だった。
「そうはいっても全然来ないじゃない?」
「僕みたいなろくでもないやつ、必要とされる方がまずいだろ?リーン?」
吸い終わったタバコを灰皿に押し付けると今度は待合室用のソファーに腰かける。
静かで、流れる時間もゆっくりな広い部屋。
薬屋と書かれた店舗は何もない空間に浮かんでいる。
ただ、漂うように。
彼が小さくあくびをすると、つられて彼女もあくびを一つ。
彼女がコーヒーでも入れましょうか?と口にする。
「・・・いや、お客さんだ。」
カエルの扉がやかましく騒ぎ、ゆっくりと開いた先からは狐のぬいぐるみを抱いた、帽子をかぶった少年が現れた。
「やぁ、魔王とその弟子。」
二人が部屋に入る前から知っていたかのように、彼はカウンターの向こう側へ移動していた。
「お久しぶりです。マルコフさん。」
少年は恭しく頭を下げる。
体勢が下がった瞬間を狙っていたのか、腕に抱えられていた狐のぬいぐるみは床に飛び降り、とことことマルコフに近づく。
「おいしいもの。なー。」
「これかい?」
マルコフはぬいぐるみが欲しているものを察し、ポケットから小さな棒付きキャンディを取り出す。
包みに包まれたそのキャンディは子供用の飴のよう。
それをぬいぐるみに渡すと、それを両手で受け取り、やや速足でソファーに駆け寄り、飛び乗る。
包み紙を破くと、そこにはまるでスノードームのようにケーキやドーナッツが舞っている飴があった。
「ありがとう。なー。」
「今日はなんのようで?」
リーンが入れてくれたコーヒーを客人たちに出し、マルコフはカウンターの椅子に腰かける。
「この間、処置処方のカードを使ったので。」
彼は大事に抱えているホルダーから本を一冊取り出す。
その本を見つめると、マルコフは椅子から腰を上げ、壁にある棚に手を伸ばす。
つかんで戻ってきた手には赤い錠剤と緑色の液体が握られていた。
それを少年の前に並べると、再びコーヒーに手を伸ばす。
「ありがとうございます。えっと、お代は・・・。」
「いらない。」
ぶっきらぼうに断るマルコフ。
それを見ながらリーンがため息をつく。
「もらっておかないと!この薬局の運営費もただじゃないのよ?」
金銭の授受は彼が見えないところで少年と白猫で行われた。
それでも格安だったが。
その部屋のいくつもの錠剤やその材料が棚に並べられ、薬局らしい光景があるが、かたや別の方向の壁を見ると大量の本が並べられ、また別の方角には大量の酒類が並んでいる。
初めて来た人はいったい何屋なのだろうと考える。
少年も最初に来た時には悩んだものだ。
彼の師匠である狐のぬいぐるみは白猫を追いかけ、彼女に歯を剥かれて威嚇されていた。
そんな静かな空気は穏やかでどこか安心させる。
そう考えているといつも白衣の男が声をかける。
「そろそろ帰った方がいい。」
マルコフは来ることを拒まないが、長居をあまり好んでいない様子だった。
「あ、長居してすいません。」
少年は急いで荷物をまとめ、狐のぬいぐるみを抱き上げる。
「ねこ、なー。なでなで、ナナナーン!」
どうも師は白猫をなでられなかったことにご立腹の様子だった。
「リーン、頼むよ。」
マルコフが真っすぐ見つめて、リーンに頼む。
それを見たリーンはしぶしぶと諦め、狐のぬいぐるみに頭を差し出す。
「やさしくな?」
マルコフが狐のぬいぐるみにそうくぎを刺すと、それを聞いてかゆっくり優しく頭をなでる。
2回。3回。
満足したのか、いつもの張り付けた笑顔がよりにこやかになる。
「ノイも。」
師匠はいたく気に入ったのか、弟子にまで撫でることを要求する。
なぜか申し訳ない気持ちになったが、弟子も猫に手を伸ばす。
「・・・あなた、大変ね?」
少し苦笑いをしたリーンが進んで弟子の手に頭をこすりつける。
ふんわりとして、サラサラの体毛は彼に安心感を与えるに十分だった。
その感触もわずかで、するりと二人の元を離れたリーンはマルコフの肩に飛び乗る。
「帰りは失敗するなよ?」
自宅に帰るのに1回失敗した彼を見送ったマルコフは静かに残ったコーヒーを飲み干す。
「・・・。」
リーンは何か言いたげに彼の顔を見つめるが、その虚無の目に何も言えない。
「僕は大丈夫だよ。」
小さくつぶやいたマルコフにリーンは小さく、そうと返す。
肩から降りたリーンはとことこと隣の部屋に移動する。
重い空気から逃げるように。
彼は残されたコーヒーカップとソーサーをカウンターの台所に入れる。
ふと、視界の端に映った写真に目を奪われる。
そこには赤いマントを羽織り、まるで、悪魔のような姿で闊歩する彼の姿。
その指輪には時計のようなものも見える。
少しだけ逡巡し、その写真立てを倒す。
「こんなところに長居しちゃいけないさ。ここは俺の贖罪の場所なのだから。」
——————————————–